AI-RANの進展状況=準備は整ったのか

3月上旬、世界最大級のモバイル技術展示会「MWCバルセロナ2025」が開催された。昨年の開催で披露されたAI-RAN(RAN(無線アクセスネットワーク)にAIを組み込む技術)が登場1周年を迎え、盛大に祝福されたようだ。どのような機会が生まれるのかに大きな注目が集まったが、一方で、先の道のりがまだ長いことも浮き彫りになっている。
AI-RANの実現に向けて共同的に「正式な」取り組みを進める動きが始まったのは、昨年の開催を目前に控えた頃のことだった。数社の大手ベンダー、通信事業者の支持で新しい団体が発足し、「AI-RANアライアンス」という体を表す名称を掲げた。創立メンバーには、AWS、Arm、エリクソン、マイクロソフト、ノキア、サムスン電子、ソフトバンク、NVIDIA、DeepSig、TモバイルUS、ノースイースタン大学が名を連ねている。
団体としての目的は、RANにAIを活用し、性能の向上や運用コストの削減、効率の向上を図る取り組みの舵取りをすること、新しい事業モデルの基盤を整えることだ。具体的には、AIを利用したRANの周波数利用効率向上やネットワーク利用効率の改善、新たなサービスを支えるエッジAIの導入などを掲げた。
それから1年、多くの通信事業者やベンダーが課題を推進し、目標に向けて前進している。
目立った活動としては、たとえば、昨秋に「AI-RANイノベーションセンター」の設立が発表されたことなどがある。米通信大手TモバイルUSとNVIDIA、エリクソン、ノキアによる共同取り組みで、クラウドRANとAIの統合開発を重点的に進めるというものだ。TモバイルUSがプレゼンテーションで説明した内容によると、目標は、クラウドRANとAIの機能を備えた統合インフラを構築すること、数百万人のモバイルユーザーに同時にサービスを提供できる水準の拡張性を持たせることだという。
「AI-RANでは、新たにAIアルゴリズムを導入することによって無線ネットワークの潜在力を最大限に引き出すことが可能になります。AIアルゴリズムの開発はSD-RANを使って迅速に行い、トレーニングはAIデータセンターで、ファインチューニングは正確なデジタルツインを使って行うことになるでしょう。周波数利用効率とエネルギー効率が劇的に改善すると考えています」
AI-RAN分野の勢いはその後も衰えることなく、今年のMWCバルセロナの開催を控えた時期にも新しい話題が登場した。米通信大手ベライゾンがサムスン、クアルコムの協力を得て、AI搭載型RAN管理アプリケーションとRIC(RANインテリジェントコントローラー)を統合したマルチベンダーシステムの展開を発表している。
この1年でAI-RANアライアンスも会員数を大きく増やし、総数は75となった。また、以前にO-RANアライアンスのトップを務めた人物を議長に任命しており、団体としての成長がうかがえる。
調査会社の指摘によると、クラウドベースのオープンRANでAIを使った導入/管理ができれば、次のような恩恵を得られる可能性があるという。マルチベンダーのディスアグリゲーション型ネットワークが抱えている課題として、オーケストレーションが複雑になるという面があるが、AIを活用すれば、従来型のRANには及ばないオープンRANの性能面を補強できる可能性があるというものだ。
ベライゾンのテクノロジープランニング担当シニアバイスプレジデント、Koeppe(アダム・ケッペ)氏が同社の取り組みについて語った。ベライゾンでは、広くクラウドネットワーク仮想化の取り組みを進めていたため、AIの活用を拡大する土台が整っているという。
「私のみるところ、前に進んでいく様子がみられるのは、当社のように先進的なクラウドプラットフォームを導入していて、その上にオーケストレーション層も構築できている場合です。当社はこちらもすでに整えています。そうした土台があって初めて、新たにAI機能を統合する方法もわかるのです。実現すれば、エンジニアチームや運用チームによるインタラクションのあり方が変わりますし、顧客体験に関するさまざまな洞察を得られるようになります。AIでネットワークの最適化プロセスにデータを供給し、顧客体験を改善することもできるでしょう」と氏。「ですが、それも、すでにクラウドベースのインフラと基地局ソフトウェアが展開されていて、オーケストレーションを実行できることが大前提です。AIというのは、そうした高度なネットワークアーキテクチャがあったうえで、その次に目指すべきステップなのです。当社ではすでに展開を終えています」
AI-RANは軌道に乗っているのか
こうした目標を目指すには、AI-RANの取り組みを継続的に進めていくことが必要だ。「次に目指すべきステップ」という言葉には、そのことがよく表れている。イベントの開催に先立って開かれたプレス向けブリーフィングの場では、レッドハットの通信向け事業担当CTO、Ian Hood(イアン・フッド)氏が見解を語った。新しい技術を全面的に導入する時というのは、若干の不安が残るものだという。
「新しいものを取り入れる時には、市場にはいつだってためらいがあるものです」と氏。オープンRANにまつわる諸課題が以前と変わらず残っていることについて語った。「私たちは、ネットワークのこの部分を自動化すること、拡張すること、事業上のこうした利点を実現することは無理なく可能だということを確かめなくてはなりません。(中略)私たちはこれをやろうとしているわけです。こういった事業に加えて、あれこれの付加価値を提供しやすくしようとしているのです。ためらいはありますが、それを乗り越えながら、業界のための取り組みが続いています」
AWSで通信向け事業を統括しているゼネラルマネージャーのChivas Nambiar(シーバス・ナンビア)氏も、同じような心情を表明している。次の大きな設備投資サイクルが来るより先に、AI-RANアライアンスの影響力が拡大し、広くAI-RANの採用が進むということにはならないのかもしれない。
「このアライアンスでは、GPUアクセラレーションを搭載したインフラでRAN機能を実行するフェーズの次は、どのようなフェーズになるかを見出そうと務めています。かなりの作業がある状態ですし、まだ話し合いとしてはごく初期の段階だと思います」と氏。「これまでにもたくさんの人が、ああでもない、こうでもないと言っていますが、個人的な予想を述べますと、実際に判断する段階に入ってくるのは、6Gへの進展が近づいてきた頃になると思っています。GPUインフラでこうした機能を実行した時に、コスト面、性能面で恩恵があるのかどうか、カスタムアクセラレーターよりもコスト面で有利なのかがわかるでしょう」
こうしたハードルがある一方で、AI-RANにはチャンスがあるというのが調査会社の見方だ。
米テラルリサーチの市場予測では、世界のAI-RAN市場の規模について、今年は17億ドル、2030年には104億ドルに成長すると予測している。「エコシステムは現在、活気に満ちた様子です」と述べている。
米ABIリサーチのアナリスト、Larbi Belkhit(ラルビ・ベルキット)氏は、最近のレポートに次のように書いている。「長期的には、通信事業者もベンダーも、業界として(AI-RANという)考え方に移行していく流れになるでしょう。オープンインターフェイスに依存せずとも実装できますし、エッジに配置したネットワーク資産を収益化するというニーズの解決も目指している技術です」。「この考え方では、(RICを)使用すると思われますが、インフラ上で実行するさまざまなAIワークロードとRANの両方を管理するには、AIオーケストレーターが必要になるでしょう」と補足した。

電気通信、5G、無線アクセスネットワーク(RAN)、エッジネットワーキングを専門とし、電気通信分野を20年以上担当している。SDxCentral入社以前は、RCR Wireless Newsの編集長を務めていた。
連絡先:dmeyer@sdxcentral.com
X(旧Twitter):@meyer_dan
LinkedIn:dmeyertime

電気通信、5G、無線アクセスネットワーク(RAN)、エッジネットワーキングを専門とし、電気通信分野を20年以上担当している。SDxCentral入社以前は、RCR Wireless Newsの編集長を務めていた。
連絡先:dmeyer@sdxcentral.com
X(旧Twitter):@meyer_dan
LinkedIn:dmeyertime
JOIN NEWSME ニュースレター購読
月に1回、newsMEのトピックスをメールで配信しています!
登録解除も簡単です。ぜひお気軽にご購読ください

KCMEの革新的な技術情報を随時発信
5G・IoT・クラウド・セキュリティ・AIなどの注目領域のコンテンツをお届けします。

KCME注目の技術領域に関するテックブログを配信しています。
KCME注目の技術領域に関するテックブログを配信しています。
RELATED ARTICLE 関連記事
-
人工知能(AI) StringerAI
 2025.12.26
2025.12.26Oracleが2026年に5万基のAMD GPUを搭載したAIスーパークラスターの導入へ
Oracleは2026年度第3四半期に、AMD In…
-
人工知能(AI) StringerAI
 2025.12.19
2025.12.19モデルコンテキストプロトコル(MCP)の概要と利点
モデルコンテキストプロトコル(Model Conte…
-
5G StringerAI
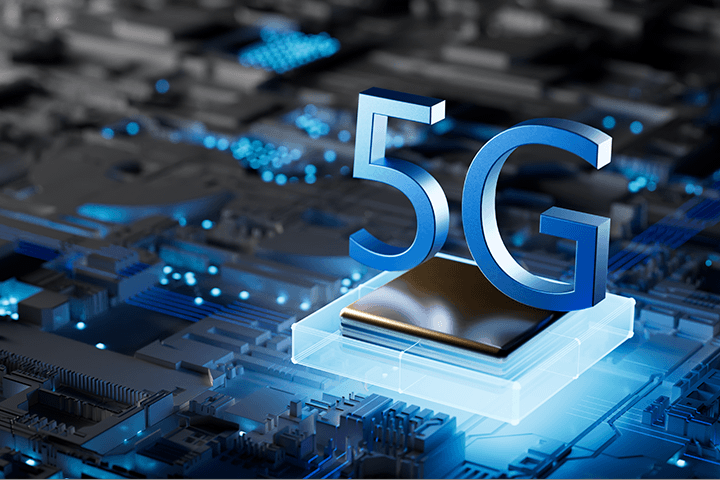 2025.12.11
2025.12.11ノキアのモバイルブロードバンドインデックス:2030年のMEA地域における5G成長を予測
ノキアは「2025年モバイルブロードバンドインデック…
-
人工知能(AI) StringerAI
 2025.12.04
2025.12.04ポッドキャストがネットワーク自動化におけるエージェンシーAIの役割を検討
Chris Wade(クリス・ウェード)氏とNick…
HOT TAG 注目タグ
RANKING 閲覧ランキング
-
 IT Dan Meyer
IT Dan MeyerBroadcomがVMwareパートナープログラムの詳細を発表
-
 IT Dan Meyer
IT Dan MeyerどうなるHPEのジュニパー買収=Juniper Mistの分離・売却はあるのか
-
 セキュリティ Nancy Liu
セキュリティ Nancy LiuSASE市場が急成長=第1四半期、首位はZscaler
-
 IT Dan Meyer
IT Dan MeyerBroadcomによるVMware製品の価格/ライセンスの変更がどうなったか
-
 スイッチング技術 Tobias Mann
スイッチング技術 Tobias Mannコパッケージドオプティクスの実用化は何年も先=専門家談
-
 ネットワーク Sean Michael Kerner
ネットワーク Sean Michael Kerner2024年における10のネットワーキング技術予測
-
 セキュリティ Tobias Mann
セキュリティ Tobias Mann米CitrixはMcAfee社、FireEye社と同じ運命を辿るのか=買収合併の後に
-
 セキュリティ Nancy Liu
セキュリティ Nancy LiuGoogleがパスキーを導入=パスワードや2段階認証からの移行を推奨
-
 ネットワーク StringerAI
ネットワーク StringerAIノキア、アルカテル・サブマリン・ネットワークス(ASN) のフランス政府への売却を完了
-
 データセンター Dan Meyer
データセンター Dan Meyerデータセンターブームはいつまで続くか=AWS, Microsoft, Googleがけん引
